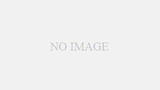「珈琲(コーヒー)って原価は数十円らしいよ」「スタバで500円するのは高すぎじゃない?」 そんな声を聞くたびに思う。コーヒーの原価を数字だけで語るのは、ちょっともったいないと。
この記事では、コーヒーの原価や原価率にまつわるさまざまな視点を紹介していく。 カフェチェーン、缶コーヒー、自家焙煎、スペシャリティなど幅広く取り上げ、「なぜ高く感じるのか?」「どうしてその価格なのか?」という素朴な疑問に寄り添いながら解き明かしていきたい。
読者は以下のような人を想定している:
- 「コーヒーってなんで高いの?」と思っている人
- 飲食店・コーヒーショップを開こうとしている人
- 原価を知って“ぼったくりじゃん”と感じてしまった人
それでは、一緒にコーヒー原価の世界を深掘りしてみよう。
目次
- 1. 一般に購入できるコーヒー生豆の原価とは?
- 2. 缶コーヒーが安い理由とは?
- 3. チェーン店のコーヒーが高くなる理由
- 4. ミルクや砂糖などのコスト
- 5. 人件費はどう価格に影響する?
- 6. 場所代がバカにならない
- 7. 原価率だけで語ると見誤る:コンタクトレンズの例
- 8. 技術料という“見えない価値”
- 9. 焙煎機やドリップマシーンなどの設備費
- 10. もしコーヒービジネスを始めたいなら
- 11. 【体験談】節約のつもりがコーヒー沼にハマった話
- 12. 原価の概算まとめ
- 13. まとめ:高いのは原価ではなく、価値だった

1. 一般に購入できる珈琲生豆の原価とは?
コーヒー生豆(なままめ)の価格は、豆の種類や品質、産地によって大きく異なる。
たとえば、ブラジル産やベトナム産のロブスタ種は、比較的安価に入手可能で、1kgあたり1,000円以下で手に入ることもある。
一方で、香りや酸味が豊かなアラビカ種のスペシャリティコーヒーともなると、価格帯はグッと上がる。 たとえば「松屋コーヒー」や「生豆本舗」では、1kgあたり1,500円〜2,000円程度でアラビカ種の豆が販売されている。
ただし、さらに品質を重視する場合、話は変わってくる。 高地栽培、手摘み、品評会での入賞歴を持つようなスペシャリティグレードの豆となると、1kgあたり3,000円〜5,000円という価格帯も珍しくない。
また、生豆は焙煎すると水分が飛び、約10〜15%ほど軽くなるため、実際に飲める焙煎豆は1kgあたり850〜900g程度になる。
2. 缶コーヒーの原価と安い理由とは?
コンビニや喫茶店で注文すると、コーヒー1杯あたりの価格は300〜600円程度が相場だ。 一方、缶コーヒーは自販機やコンビニで100円〜150円程度で買える。この価格差に、驚いたことがある人も多いだろう。
「え?この味でこの値段?」と感じるほど安く感じるのは、手渡しで淹れてもらうコーヒーとのギャップがあるからなのだ。
この安さの理由は、大量生産と徹底したコスト管理にある。 使用される豆は、主にロブスタ種が中心で、コストの安いブレンド構成。 また、抽出後に保存料を加え、長期保存可能にすることでロスを限界まで減らしている。
さらに、缶コーヒーには「味の均一性=安定品質」が絶対条件。 どのロットでも同じ味でなければいけないという性質上、風味の奥行きや複雑さを求めるよりも、味の安定性>おいしさとなりがちで、 そのため「おいしくない」と感じる人も一定数いるのは事実である。
3. チェーン店のコーヒーが高くなる理由
全国展開するカフェチェーンでは、1杯あたり300〜500円の価格帯が一般的だ。
たとえば、「スターバックス」では”サードプレイス(第三の居場所)”というコンセプトを掲げ、居心地の良さやブランド体験を重視している。丁寧な接客、落ち着いたインテリア、Wi-Fi完備などの環境がその価格に反映されている。
また、「タリーズコーヒー」では一部の店舗でハンドドリップを提供し、品質と接客に力を入れている。「サンマルクカフェ」では焼きたてパンとセットでくつろげる空間を提供しており、その価格にはドリンク代以上の「居心地代」が含まれているとも言えるだろう。
さらに、設備投資や人材教育、オーダーシステムの導入などの運営コストも馬鹿にできない。チェーン店ではモバイルオーダー、キャッシュレス決済、ポイント制度の導入など、IT投資による利便性向上にもコストがかかっている。、オーダーシステムの導入などの運営コストも馬鹿にできない。 チェーン店ではモバイルオーダー、キャッシュレス決済、ポイント制度の導入など、 IT投資による利便性向上にもコストがかかっている。

4. ミルクや砂糖などのコスト
カフェラテやキャラメルマキアートなど、ミルクやシロップを多く使うメニューでは、豆よりもミルクの方が高くつくこともある。
業務用で品質の高いミルクを使えば、1杯あたり50〜80円程度。 砂糖やシロップも含めれば、トッピング材料だけで100円近くになるケースもある。
5. 人件費はどう価格に影響する?
コーヒー1杯に対する人件費は見えにくいが、店舗運営には欠かせない。
都市部のカフェであれば、時給は1,100〜1,500円。仮にスタッフ1人が1時間に30杯コーヒーを提供するとして、 時給1,200円÷30杯=1杯あたり40円の人件費がかかっている計算になる。
もちろんこれは単純計算で、実際には仕込み、片付け、オーダー対応などの時間も含まれるため、実質60〜80円以上かかっているケースも珍しくない。
6. 場所代がバカにならない
コーヒー価格に大きく影響するのが「場所代」、つまり店舗の家賃だ。
駅前や繁華街に出店する場合、家賃は月数十万〜百万円以上になることもある。 さらに、初期投資として必要な内装・改装費も見逃せない。店舗のデザインやカウンター設備、電気工事、水道・排気設備の整備など、開業時に数百万円規模の支出がかかるケースも珍しくない。
このようなコストは「カフェの雰囲気づくり」や「利便性」に必要な投資でもあり、当然その分はコーヒー価格に転嫁される。
駅前や繁華街に出店する場合、家賃は月数十万〜百万円以上になることもある。 このコストは「カフェの雰囲気づくり」や「利便性」に必要な投資でもあるが、当然その分はコーヒー価格に転嫁される。
7. 原価率だけで語ると見誤る:コンタクトレンズの例
コーヒーの原価率は**15〜30%**が一般的とされる。 一見すると「高いな」と感じるかもしれないが、これでも飲食業界の中ではむしろ健全な部類だ。
たとえばコンタクトレンズや化粧品のように、原価率が5%以下というジャンルも存在する。 つまり、原価だけで「高い/安い」と判断するのは非常にリスキーなのである。
8. 技術料という“見えない価値”
コーヒーの抽出や焙煎には、高い専門性と技術力が求められる。
ハンドドリップひとつとっても、お湯の温度、注ぎ方、タイミング、挽き目の調整など、緻密な調整が必要。 これを日々こなすバリスタたちのスキルは、価格に含まれて然るべき「技術料」だ。
料理人の味付けと同じく、「誰が淹れるか」で味が変わる。それがコーヒーの奥深さである。
9. 焙煎機やドリップマシーンなどの設備費
焙煎機はピンキリだが、家庭用でも高性能な機種となるとそれなりに高価である。 たとえば私が使っている「Sandbox Smart R2」は、家庭用ながら定価約38万円。
この焙煎機を週2回、毎回1kgの生豆を焙煎し、それを10年間使用したと仮定しよう。 生豆から焙煎すると約10%の重量ロスがあるため、1kgの生豆から得られる焙煎豆はおよそ900g。
コーヒー1杯に使う焙煎豆が15gであるとすれば、10年間で約6,240杯分の豆が得られる計算になる。 このとき、1杯あたりに換算される焙煎機本体の設備コストは約6.09円。 なお、これは電気代やメンテナンス費用を含まない本体価格のみでの計算である。

10. もしコーヒービジネスを始めたいなら
これから「コーヒーで商売してみたいな」と考えている人に伝えたいのは、原価だけ見て始めるのはとても危険ということ。
場所代や人件費を考えずに、「この原価なら儲かる!」と思っても、現実はそう甘くない。
もし最初に試すなら、自宅で生豆を焙煎し、ネットで販売してみるというスタイルがおすすめ。 人件費も家賃もかからず、低リスクで始められる。
ちなみに筆者自身も、今まさにその準備をしているところである。 理想の焙煎プロファイルを試行錯誤しながら、「おいしい!」と言ってもらえる豆を届けられる日を夢見ている。
11. 【体験談】節約のつもりがコーヒー沼にハマった話
私が焙煎を始めたきっかけは、ハンドドリップコーヒーに目覚めたことだった。
「毎回豆を買うのって、結構高いな…」と感じていたある日、ふとひらめいたのだ。 「自分で豆を焙煎すれば、もっと安く済むんじゃないか?」と。
もちろん、おいしいコーヒーを飲みたいという思いもあった(ブラックコーヒーはおいしい?:元・砂糖・ミルク必須派が辿り着いた答え)が、正直に言えば“お金がかかる”ことへの抵抗感も理由のひとつだった。 実際に松屋コーヒーや生豆本舗のサイトを見てみると、やはり生豆の価格は安い。
「多少面倒でも、鍋で焙煎すればなんとかなるはず」 そう思って、私の焙煎人生がスタートした。
……のはずが、最終的に私はSandbox Smart R2を購入してしまった。 気づけば節約のつもりが、かなり高価な道具を次々と買い揃えることに。
原価にこだわる“原価厨”だったはずの自分が、結果的にコマンダンテやROKエスプレッソなどの器具にも手を出し、見事に沼にハマっていった。
「豆販売を始めれば、いずれ元は取れる…!」 そう自分に言い聞かせながら、今日もまた器具に囲まれて、理想の味を追い求めている。
12. 原価の概算まとめ
最後に、ここまで紹介してきた要素をもとに、コーヒー1杯あたりの原価をざっくりと試算してみよう(フェルミ推定なので、注意してください)。
| 項目 | 原価(円) |
|---|---|
| 生豆(アラビカ種1500円/kg想定) | 約25円 |
| ミルク・砂糖(ミルク系の場合) | 約70円 |
| 人件費 | 約70円 |
| 設備費(Sandbox Smart R2換算) | 約6.1円 |
| 場所代(家賃・水光熱を含めた仮定値) | 約50円 |
| 技術料(抽出・焙煎スキルの価値) | 約30円 |
| 合計 | 約251円 |
もちろんこれは一例で、店舗の形態や地域、豆の種類によって大きく変動するが、こうしてみると「コーヒーは原価数十円」という印象がいかに表面的かがわかる。
人件費は1人で考えており、ワンオペ1時間30杯出すのは結構大変だろう。
また豆とミルク砂糖以外は固定費に分類されるので、店舗をやって流行らなければ赤字になるのは言うまでもない。
13. まとめ:高いのは原価ではなく、価値だった
コーヒーは、確かに生豆だけを見れば「安い」と感じるかもしれない。 しかし、焙煎・抽出・接客・設備・空間といったすべての要素が合わさって、あの一杯はできている。
だからこそ、価格には「豆」だけでなく「体験」も含まれているのだ。
高く感じるかもしれないけれど、そこにはきっと理由がある。 それを知ることで、コーヒーの味わいもまた、少し変わって感じられるかもしれない。